二月。空気。これがもう、言語道断に冷たい。いや冷たいなんて生ぬるい表現では足りない。それは無数の細工針が、わたしの皮膚という皮膚を、まるで熱心な刺繍作家のようにズブズブと、あるいはブスブスと、遠慮も会釈もなく縫い合わせにくるような感覚だ。わが社屋の名ばかり居住フロアは冷蔵庫と化していた。しかも入っているのは夢とか希望じゃなくて、節約という名の執念である。
そしてその寒さに似合わず、部屋には濃いカカオの匂いが漂っている。場違いという言葉を殴って黙らせるほどに濃厚。テーブルの真ん中には百貨店の包装紙を脱がされた豪奢なチョコレートの箱。脱がされたってのがもう、なんか、変な感じだ。裸の高級チョコ。品があるのかないのか分からない。
箱の向こう、社長のカネア様が深海にまで沈む嘆息を漏らしている。元・大企業の社長令嬢。現・この氷の箱の社長。社長という肩書きも、今や賞味期限の切れた飴玉のように、口に転がしても味気ない。
「……はぁ。ゴロー様……いったい今頃、宇宙のどこにいらっしゃるのかしら」
彼女の想い人、通称「カニ頭」は行方不明だ。彼が働くYATは現在休業中。わたしに言わせれば、同業他社が休んでいる隙に市場をかっさらうのは商売の鉄則だが、彼女の脳内にある経済学の教科書には「恋の欠乏」というチャプターしか存在しないらしい。
「せっかく、奮発して最高級のトリュフを用意しましたのに……。渡すお相手がいなくては、ただのカロリーの塊ですわ」
その横で、副社長──実質的には"雑用係+名誉副社長"というのが正確な肩書き──のわたしは、すり切れたモップを握りしめたまま動きを止めていた。
(カネア様……)
わたしの内心は、梅雨どきの床下収納のように湿っぽい。それでも床は磨かねばならないし、会社の経営も支えねばならない。特売の卵で一喜一憂し、薄い毛布を分け合う相手は宇宙のどこかにいるカニ頭ではなく、盤石の献身を誓うこのわたしなのだから──などと、言えるはずもない。
「……社長。そのチョコ、賞味期限も短いですし、どうなさるおつもりで?」
「うるさいわねダニエル! わかってますわよ、そんなこと!」
語尾で鞭を打つカネア様に、わたしはいつものように、よく訓練された低姿勢でうなずくしかない。だが彼女が漏らした次のひと言が、わたしの忍耐という名の、今にもちぎれそうな細い糸を引きちぎった。
「はあ…ゴロー様が居ないとなると…チョコを渡す相手なんて……」
「……誰も、いませんものね」
「わたしが、おりますよ!!!!」
その叫び声は、自分の口から出たとは思えないほど大きく、そして絶望的なほど愚かだった。窓ガラスがビリビリと震え、平和に眠っていた埃が舞い上がる。わたしはモップを放り出し、テーブルに両手をついてカネア様に詰め寄っていた。
「……え?」
「カニ頭のヤローは今頃宇宙のどこかで蟹味噌でも啜ってるんでしょう!でも! わたしは! ここに!! います!!!」
カネア様が目を丸くしている。わたしは肩で息をしながら、自分が取り返しのつかない、とんでもない失態を犯したことに気づいた。心臓が、故障して脱水モードから戻れなくなった洗濯機のように、肋骨を叩いている。
(言っちまった……!!!)
思った瞬間にはもう遅い。冷や汗が背筋を滑り落ちる。滑り台みたいに。
「だ、ダニエル……?」
数秒間、古い掛け時計の秒針だけがチクタクと鳴る。静寂というのは音がないんじゃなくて、音が一本だけ残る状態だ。その静寂の中、わたしは慌てて支離滅裂な言葉を継ぎ足した。
「そ、そうです!もったいない精神です!SDGsです!!その高級チョコを廃棄するなど、元・大企業の社長令嬢としてあるまじき行為!ですから、このわたしが!ゴミ箱の代わりに!!僭越ながら処理班として立候補した次第でして!!」
自分でも驚くほど苦しい言い訳だ。穴の開いたバケツでタイタニック号を救おうとするようなものだ。しかし、カネア様の瞳に、奇妙で、こちらの破滅を楽しむような少しばかりいたずらっぽい光が宿った。
「……ふーん?」
彼女は唇の端を悪戯っぽく曲げ、チョコレートの箱から一際美しいハート形のトリュフを摘み上げた。
「ゴミ箱、ねぇ……。随分と、主張の激しいゴミ箱ですこと」
「うっ……」
「いいわ。そこまで言うなら、特別にあげないこともなくてよ?」
彼女はトリュフをそっと掲げ、わたしの口元まで近づける。
「ほら。あーん、なさい。ゴミ箱さん」
「えっ……い、いえ、自分の手で頂きますので……」
「社長命令ですわよ、ダニエル?」
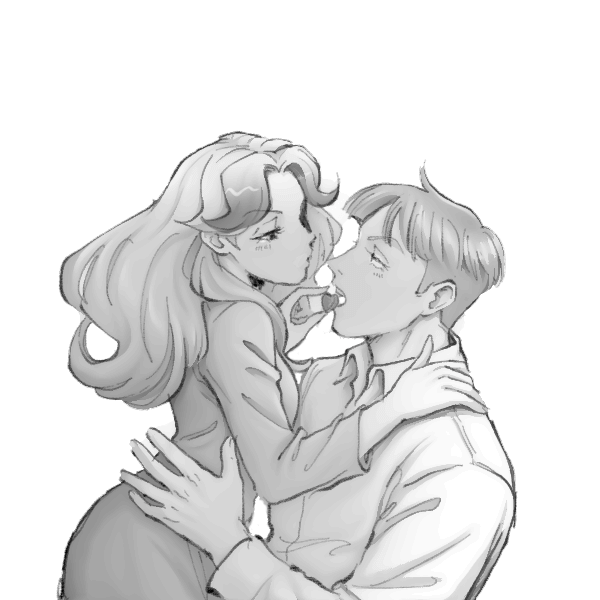 そこには逃げ場などなかった。わたしは観念し、親鳥を待つ哀れな雛のように口を開けた。彼女の指先がかすかに触れ、濃厚なカカオと、いかにも高そうな洋酒の香りが舌の上で爆発した。
そこには逃げ場などなかった。わたしは観念し、親鳥を待つ哀れな雛のように口を開けた。彼女の指先がかすかに触れ、濃厚なカカオと、いかにも高そうな洋酒の香りが舌の上で爆発した。
「……ん」
洋酒の香りでわたしの乏しい理性は、紙切れのように湿ってふやけた。彼女は潤んだ瞳で、じっとこちらの咀嚼を見守っている。その視線は、高級チョコの甘さよりも強烈に脳を揺さぶる。
「……どう? おいしい?」
「……はい。とても。地獄のように、甘いです」
声が震えないように固定するだけで、わたしの全エネルギーが消費された。
「そう。……なら、よかったわ」
彼女は照れ隠しみたいに、自分の分をひと口で頬張った。ガナッシュが溶けるよりも速く、頬が朱に染まる。寒い部屋で、そこだけが春のようである。
「まだたくさんありますからね。……全部、あなたが責任を持って食べなさいよね、ダニエル」
「……はい、カネア様。喜んで」
わたしの胸の中では、壊れたアラームのような鼓動が、静まり返った極寒の部屋に場違いなほど響き渡っていた。
いつか彼女が、幻影を追いかけるのを諦め、目の前で体温と忠誠心を垂れ流しているこのわたしを直視せざるを得なくなるその日まで。わたしはこの、最高級のゴミ箱という称号を勲章のように胸に張り付け、彼女のそばに居座り続けるつもりだ。たとえ今のわたしが、ただの「チョコを回収するだけの装置」だとしても。不在の王子よりは、目の前の動く廃棄物の方が、冬の夜にはいくらか役に立つはずなのだから。
そしてその寒さに似合わず、部屋には濃いカカオの匂いが漂っている。場違いという言葉を殴って黙らせるほどに濃厚。テーブルの真ん中には百貨店の包装紙を脱がされた豪奢なチョコレートの箱。脱がされたってのがもう、なんか、変な感じだ。裸の高級チョコ。品があるのかないのか分からない。
箱の向こう、社長のカネア様が深海にまで沈む嘆息を漏らしている。元・大企業の社長令嬢。現・この氷の箱の社長。社長という肩書きも、今や賞味期限の切れた飴玉のように、口に転がしても味気ない。
「……はぁ。ゴロー様……いったい今頃、宇宙のどこにいらっしゃるのかしら」
彼女の想い人、通称「カニ頭」は行方不明だ。彼が働くYATは現在休業中。わたしに言わせれば、同業他社が休んでいる隙に市場をかっさらうのは商売の鉄則だが、彼女の脳内にある経済学の教科書には「恋の欠乏」というチャプターしか存在しないらしい。
「せっかく、奮発して最高級のトリュフを用意しましたのに……。渡すお相手がいなくては、ただのカロリーの塊ですわ」
その横で、副社長──実質的には"雑用係+名誉副社長"というのが正確な肩書き──のわたしは、すり切れたモップを握りしめたまま動きを止めていた。
(カネア様……)
わたしの内心は、梅雨どきの床下収納のように湿っぽい。それでも床は磨かねばならないし、会社の経営も支えねばならない。特売の卵で一喜一憂し、薄い毛布を分け合う相手は宇宙のどこかにいるカニ頭ではなく、盤石の献身を誓うこのわたしなのだから──などと、言えるはずもない。
「……社長。そのチョコ、賞味期限も短いですし、どうなさるおつもりで?」
「うるさいわねダニエル! わかってますわよ、そんなこと!」
語尾で鞭を打つカネア様に、わたしはいつものように、よく訓練された低姿勢でうなずくしかない。だが彼女が漏らした次のひと言が、わたしの忍耐という名の、今にもちぎれそうな細い糸を引きちぎった。
「はあ…ゴロー様が居ないとなると…チョコを渡す相手なんて……」
「……誰も、いませんものね」
「わたしが、おりますよ!!!!」
その叫び声は、自分の口から出たとは思えないほど大きく、そして絶望的なほど愚かだった。窓ガラスがビリビリと震え、平和に眠っていた埃が舞い上がる。わたしはモップを放り出し、テーブルに両手をついてカネア様に詰め寄っていた。
「……え?」
「カニ頭のヤローは今頃宇宙のどこかで蟹味噌でも啜ってるんでしょう!でも! わたしは! ここに!! います!!!」
カネア様が目を丸くしている。わたしは肩で息をしながら、自分が取り返しのつかない、とんでもない失態を犯したことに気づいた。心臓が、故障して脱水モードから戻れなくなった洗濯機のように、肋骨を叩いている。
(言っちまった……!!!)
思った瞬間にはもう遅い。冷や汗が背筋を滑り落ちる。滑り台みたいに。
「だ、ダニエル……?」
数秒間、古い掛け時計の秒針だけがチクタクと鳴る。静寂というのは音がないんじゃなくて、音が一本だけ残る状態だ。その静寂の中、わたしは慌てて支離滅裂な言葉を継ぎ足した。
「そ、そうです!もったいない精神です!SDGsです!!その高級チョコを廃棄するなど、元・大企業の社長令嬢としてあるまじき行為!ですから、このわたしが!ゴミ箱の代わりに!!僭越ながら処理班として立候補した次第でして!!」
自分でも驚くほど苦しい言い訳だ。穴の開いたバケツでタイタニック号を救おうとするようなものだ。しかし、カネア様の瞳に、奇妙で、こちらの破滅を楽しむような少しばかりいたずらっぽい光が宿った。
「……ふーん?」
彼女は唇の端を悪戯っぽく曲げ、チョコレートの箱から一際美しいハート形のトリュフを摘み上げた。
「ゴミ箱、ねぇ……。随分と、主張の激しいゴミ箱ですこと」
「うっ……」
「いいわ。そこまで言うなら、特別にあげないこともなくてよ?」
彼女はトリュフをそっと掲げ、わたしの口元まで近づける。
「ほら。あーん、なさい。ゴミ箱さん」
「えっ……い、いえ、自分の手で頂きますので……」
「社長命令ですわよ、ダニエル?」
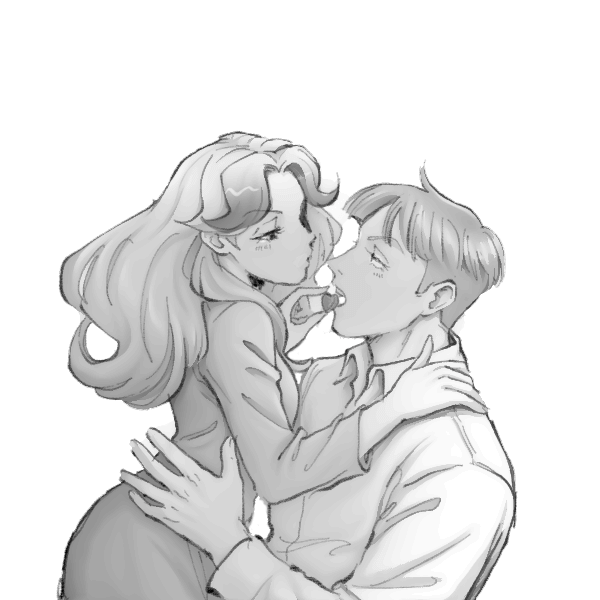 そこには逃げ場などなかった。わたしは観念し、親鳥を待つ哀れな雛のように口を開けた。彼女の指先がかすかに触れ、濃厚なカカオと、いかにも高そうな洋酒の香りが舌の上で爆発した。
そこには逃げ場などなかった。わたしは観念し、親鳥を待つ哀れな雛のように口を開けた。彼女の指先がかすかに触れ、濃厚なカカオと、いかにも高そうな洋酒の香りが舌の上で爆発した。「……ん」
洋酒の香りでわたしの乏しい理性は、紙切れのように湿ってふやけた。彼女は潤んだ瞳で、じっとこちらの咀嚼を見守っている。その視線は、高級チョコの甘さよりも強烈に脳を揺さぶる。
「……どう? おいしい?」
「……はい。とても。地獄のように、甘いです」
声が震えないように固定するだけで、わたしの全エネルギーが消費された。
「そう。……なら、よかったわ」
彼女は照れ隠しみたいに、自分の分をひと口で頬張った。ガナッシュが溶けるよりも速く、頬が朱に染まる。寒い部屋で、そこだけが春のようである。
「まだたくさんありますからね。……全部、あなたが責任を持って食べなさいよね、ダニエル」
「……はい、カネア様。喜んで」
わたしの胸の中では、壊れたアラームのような鼓動が、静まり返った極寒の部屋に場違いなほど響き渡っていた。
いつか彼女が、幻影を追いかけるのを諦め、目の前で体温と忠誠心を垂れ流しているこのわたしを直視せざるを得なくなるその日まで。わたしはこの、最高級のゴミ箱という称号を勲章のように胸に張り付け、彼女のそばに居座り続けるつもりだ。たとえ今のわたしが、ただの「チョコを回収するだけの装置」だとしても。不在の王子よりは、目の前の動く廃棄物の方が、冬の夜にはいくらか役に立つはずなのだから。
